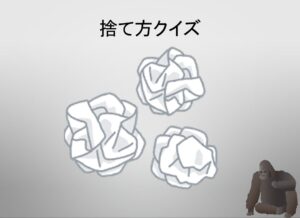「福祉」という共通言語で、色々な理論や手法を知る。
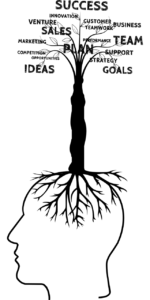
こんにちは、コロンです!
先日、「オンライン福祉系のお茶会」に参加しました。
そこで出た様々な理論や手法が面白かったので、ここで共有。
堅い内容ですが、興味のある方は、以下をお読みくだされ〜!
・まず「LT(ライトニングトーク)」。
『ライトニングトーク』という手法を使って
参加者各自が自分の好きなテーマを話をしてから意見交換するという茶話会でした。
LT(ライトニングトーク)とは?
カンファレンスやフォーラムなどで行われる短いプレゼンテーションのこと。様々な形式があるが、持ち時間が5分という制約が広く共有されている。(Wikipedia)
詳しく知りたい方は、こちらも参照↓
https://note.com/mc_kurita/n/n5db9cba224b5
・LT「自分の個別支援計画立ててる?」が意見交換のテーマ
私たち福祉職の人間は、利用者さん、メンバーさんと
「将来は、どうしたいですか〜?」とか
「○○が出来るように、△△に取り組んでみましょう!」とか
「お金を貯められるように、○○しましょう」とか
目標や計画を立てています。
人には「これが必要だ!」とか「こうした方がいい」など
先の数ヶ月、数年後のことを事細かく具体的に考えて、目標設定し
実行計画を立てて、できたかできなかった確認までしているのに
いざ自分のこととなると
「なんとかなるっしょ!」と、いう感じ。(私も!!!)
でもこれって、福祉系あるあるで
人には熱意と強い想いを持って、その人の人生を全力で考えるのに
いざ自分は・・・・というやつでは?というのがテーマ。
こちらのテーマ発表者の方は、今は公務員として福祉事業所の設備管理関係の業務をしているが
6年後にはコーヒーショップで起業する予定で、起業やコーヒー、ファイナンスなどの
様々な勉強をしつつ、同じ思いの方々とオンライン勉強会を主催するなどしているそうです。
自分の人生に「個別支援計画」を立てて実行し、セルフや仲間の力を借りて
モニタリング、アセスメントしている人でした。
ただ、この方も学生時代は「何もやりたいことがなく」・・・とうタイプだったそうで。
流れで一般職に就職し、数年後「保育士になる!」と決めて再勉強、保育士取得。
そして、今は家族と次の夢に向けて〜と頑張っているとのこと。
一般職と福祉職の両方を経験し、自分の将来に向けて計画を立て実行している発表者から見ると
同じ福祉系業界人は
『自分は?なんとかなるっしょ!!』精神の人が多いそうで。
「自分の課題と他者の課題を割り切って考えて、他者に全力でエネルギーを注げる尊敬する人たち」
なんだそうです。
(だから、超リスペクト!って言ってました)
うーむ、そう言われると。
自分の仕事の計画はあっても、生活も含めた計画って、あまり考えてなかった・・・。
でも、すごく特別な人生や生活じゃなくても、未来に向けての計画って大切なのは
業務上強く強く理解しているところです。
ここで、他の参加者から出てきた意見が「ブランドハプンスタンス理論」。
なんじゃそれ?
・「ブランドハプンスタンス理論」
・ 「計画された偶発性」理論のこと。
・ スタンフォード大学のジョン・D.・クランボルツ教授が提唱したキャリア論である。
・ キャリアは偶然の出来事、予期せぬ出来事に対し、最善を尽くし対応することを積み重ねることで形成されるというもの。(コトバンク)
詳しく知りたい人はこちらも↓
https://mutsubi-a.jp/itsuka/info-itsukka/20181220/
「キャリアの8割は当初予想していなかった偶発的なことで決定される」そして「偶然を計画的に設計することで、キャリアをより良いものにしようとする」という理論。
確かに、いくら自分の人生に計画を立てても、計画通りには行かないことも私たちはよく分かっています。
だから、あえて「計画なんて、別になくてもダイジョウブイ!」と思っている所も往々にして・・・。
この理論では、5つの行動特性を持っている人は、計画的偶発性が働きやすいそうです。
- 好奇心[Curiosity] →新しいことに挑戦する
- 持続性[Persistence] →失敗しても頑張る
- 柔軟性[Flexibility] →自分の状況や姿勢をどんどん変化していける
- 楽観性[Optimism] →新しいことに対し、自分はできると思える
- 冒険心[Risk Taking →結果を恐れずに行動する
福祉のお仕事は、人の幸福に関わるお仕事。
この5つの行動って、とても大切で日頃から実践していたり、この思いで支援業務に関わっている人
とても多いのではと思います。
だから、自分の個別支援計画は立ててないけど
日頃から5つの行動特性で仕事をしているので
他者の人生に熱意を持って関わっていけるのかもしれませんね〜。
(なんの根拠もないですが〜)
・「福祉」という言語を使って、福祉以外の色々な理論や考えや手法を知る。
このオンラインお茶会の参加者は、
東京(公務員の福祉事業所管理業務)、奈良(保育士)、千葉(知財)、北海道(私)の4名。
全く違う地域、職種、年齢、経験の4名でしたが
「福祉」という共通言語と、色々な立場、角度からみる福祉への熱い想いや意見が行きする
「濃いお茶会」でした。
このテーマ以外にも、
集団保育と自由保育について
認知行動療法について
そもそも福祉の定義とは?
など、日頃は話題に上がらないテーマで知識を共有し、考えを深めることが出来ました。
LTのような手法を使って、職場やチームの仲間とそれぞれ興味のあるテーマで話をすると
今抱えている課題や新しい取り組みへのヒントが増えるかも!
そして、知らなかった理論や知識を学ぶきっかけにもなりそうです。
♥♥♥イコロン村のおしらせ♥♥♥

イコロン村の「にじいろショップ ウエカルパ」では
石狩市内、近郊の作家さんの作品を展示販売しております。